セント・アンデレ・クロス(6)
水俣を訪れました
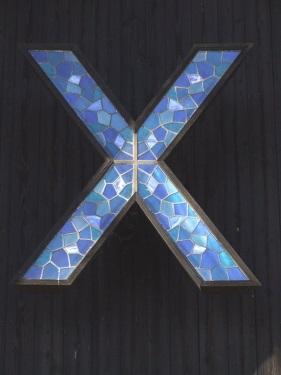
先日、熊本YMCAの総主事の退任式と就任式に出席し、その後退任された光永(みつなが)前総主事に故郷である水俣に連れて行っていただきました。水俣湾に面した国立水俣病研究センターや、水俣病資料館を見学させていただきました。昨日までの肌寒い日から一転して青空のこの日は、「西梅」らしいすがすがしい風と空と海が美しく映えわたっていました。かつてここで多くの人々が苦しみ、亡くなっていかれ今なおその被害に苦しんでおられる方がいます。
リアス式海岸のこの地は不知火湾の中でも魚が産卵場所とするいわゆる「魚の湧いてくるような」豊かな水産資源の村であったそうです。その豊かな海が工場排水によって流された水銀によって汚染され、食料の魚を通して多くの人々が水銀中毒の被害にあわれました。チッソは自らの工場排水がこの奇病の原因であるらしいとなってからも排水を続けたそうです。
高度経済成長のはじまりの中で資源や環境は無限のもの、そう勘違いしていた人間の時代が、大海に流せば消えるであろうと想像し、そうでないことがわかってもなすすべなく操業を続けなければならなかった無責任、これらが招いた大惨事でありました。
これらのことから資源には限りがあること、汚された環境は簡単には戻らないデリケートなものであることを改めて学びました。自然や環境を大切にしてゆかなばならない、その為にも自分たちの行いを振り返らなければならないときれいな海と空を味わって感じさせられました。
(水俣市は現在は水銀を含んだ土壌を掬い上げ、海に広がらないように囲いをしたうえで埋め立てて1992年に工事を終え、現在では安全な場所になっています。土地や出身地での差別にならない配慮も私たちには必要です。)
文/滋賀YMCA総主事 久保田展史


